RFIDを活用したICタグ物品管理の基礎を解説!
アストロラボ株式会社
「社内の備品管理が大変」「どこに何があるのかすぐに把握できない」といった悩みを抱えていませんか?企業や組織で備品を適切に管理することは、業務の効率化やコスト削減につながる重要な課題です。しかし、手作業での管理やバーコードの読み取りでは、作業の手間がかかるうえ、ヒューマンエラーのリスクも避けられません。
そんな備品管理の課題を解決する手段として注目されているのが、RFID(Radio Frequency Identification)とICタグの活用です。これらの技術を導入することで、非接触でのデータ読み取り、一括スキャン、リアルタイムの在庫把握などが可能になり、備品管理の効率が大きく向上します。
本記事では、ICタグやRFIDの基本から、活用方法、種類、選び方まで詳しく解説します。総務部門で備品管理を担当する方や、業務の効率化を検討している方にとって役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までお読みください。
ICタグとは?
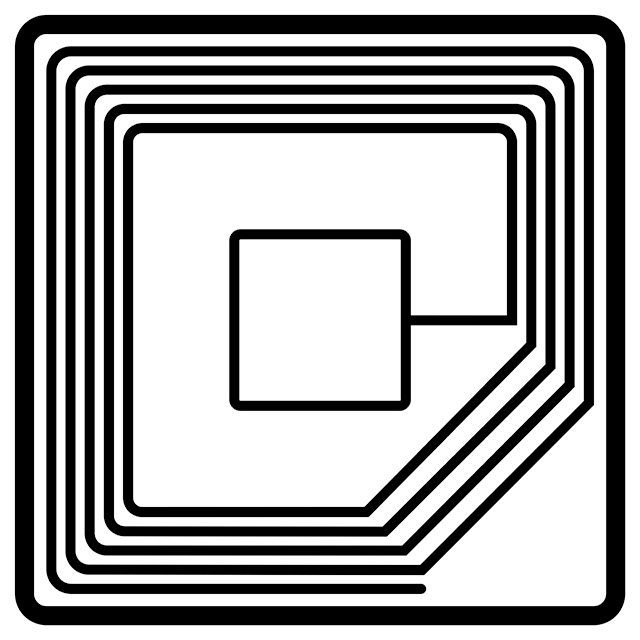
ICタグとは、無線通信機能を持つタグのことで、電波を利用して個々の物品を識別・管理するためのデバイスです。「無線タグ」や「RFタグ」、「RFIDタグ」などと呼ばれることもありますが、基本的には同じものを指します。ICタグを活用することで、複数のタグを同時に読み取ったり、タグが見えない状態でも情報を取得したりすることが可能となり、備品管理業務の効率化に大いに役立ちます。
無線タグや無線ICタグとの違い
「無線タグ」や「無線ICタグ」といった呼称は、ICタグと同義で使われることが一般的です。特に明確な違いはなく、業界や用途によって呼び方が変わる程度と考えて差し支えありません。ただし、「ICタグ」という表現は、電子チップが埋め込まれたものを指すことが多く、単なる識別タグとは異なります。
RFIDとは?
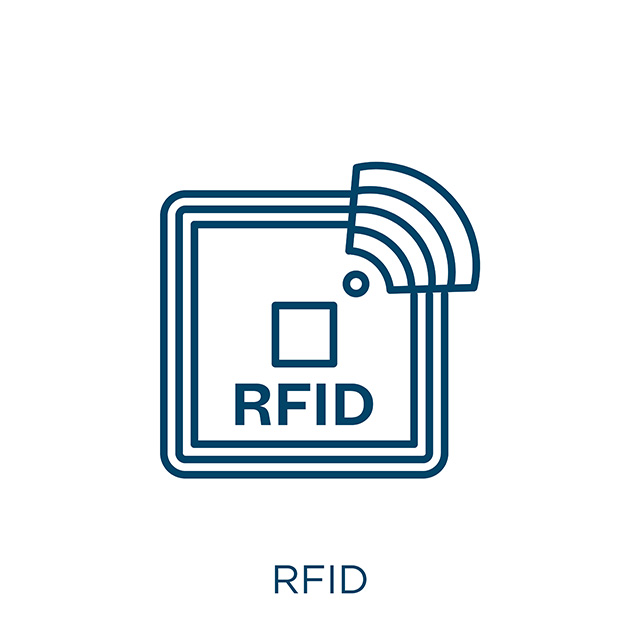
RFID(Radio Frequency Identification)とは、無線周波数を利用して情報をやり取りし、備品や人を識別・管理する技術のことです。バーコードやQRコードと異なり、電波を使用するため、タグが目視できない状態でもデータの取得が可能です。物流や小売、医療、製造業など幅広い分野で利用され、効率的なデータ管理に活用されています。
RFIDの構成要件(RFIDとICタグの違い)
RFIDは「ICタグ」「RFIDリーダー」「処理システム」の3つの要素で構成されています。ICタグは情報を保持し、RFIDリーダーはその情報を読み取ります。読み取られたデータは処理システムに送られ、在庫管理や備品管理など、さまざまな業務に活用されます。つまり、ICタグはRFIDの一部であり、RFIDはこれらの要素が組み合わさった全体を指します。
QRコードやバーコードとの違い
RFIDとQRコードやバーコードとの大きな違いは、情報の読み取り方法と効率性にあります。QRコードやバーコードは、リーダーでコードを直接スキャンする必要があり、一度に一つのコードしか読み取れません。また、コードが汚れたり損傷したりすると、読み取りが困難になることもあります。一方、RFIDは電波を利用して非接触で情報を取得でき、複数のICタグを同時に読み取ることが可能です。さらに、タグが見えない状態や、多少の汚れがあっても読み取りに支障をきたしません。
RFIDを活用した備品管理なら備品管理クラウド
『備品管理クラウド』は、RFIDを利用した棚卸機能を提供しており、一括で備品の所在を確認することで棚卸作業を効率化することができます。
少しでも気になる方は下記よりお気軽にお問い合わせください。
RFIDとICタグの活用場面
RFIDとICタグは、さまざまな分野で活用されています。例えば、アパレル業界では商品の在庫管理やセルフ会計、物流業界では荷物の追跡や入出庫管理、医療業界では医薬品や医療機器の管理など、多岐にわたります。特に、在庫や備品の管理においては、RFIDとICタグの導入により、業務効率の向上やヒューマンエラーの削減が期待できます。
行政主導のICタグ企業活用事例
日本では、経済産業省が2017年に「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」を発表し、2025年までにコンビニ大手5社の全商品に電子タグを導入する計画が進められています。これにより、レジ業務の効率化や人手不足の解消、万引き防止、食品ロスの削減などが期待されています。
ICタグの種類
ICタグは、その構造や機能によってさまざまな種類があります。用途や環境に応じて適切なタグを選ぶことが重要です。
ICタグの選び方
ICタグを選ぶ際には、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。
・使用環境:屋内外の別、温度や湿度、金属や水の影響など。
・読み取り距離:近距離での読み取りか、遠距離での読み取りが必要か。
・タグのサイズや形状:貼り付ける対象物の大きさや形状に適しているか。
・コスト:予算に見合った価格であるか。
備品管理にはRFIDを活用するのがおすすめ

ICタグとRFIDを活用することで、備品管理が大幅に効率化できます。具体的には、以下のようなメリットがあります。
業務効率化
一括読み取りにより、棚卸し作業などの備品管理業務がスムーズになります。
備品管理業務の精度向上
手作業による記入ミスや記入漏れがなくなり、備品管理業務の精度が向上します。
非接触でのデータ読み取り
RFIDは電波を利用して非接触で情報を取得でき、複数のICタグを同時に読み取ることが可能です。また、多少の汚れがあっても読み取りに支障をきたしません。
隠れていても読み取り可能
RFIDは電波を利用して非接触で情報を取得できるため、タグが見えない状態でも読み取りに支障をきたしません。例えば、大量の備品が梱包された状態でも読み取りが可能です。
簡単なデータ書き換え
RFIDはICタグの情報を容易に更新できます。
高いセキュリティ
偽造防止機能も備えています。
紛失時の位置検知
ビーコン機能を活用して位置情報を検知できるサービスもあります。
RFIDを活用した備品管理なら備品管理クラウド
アストロラボの「備品管理クラウド」には、登録したアイテムの棚卸機能があります。
棚卸をすることで、アイテムの個数や場所など、備品管理クラウドにあらかじめ登録しておいた管理台帳としての情報と、実際のアイテムの状態が一致しているかどうか確認できます。
工具など所在の確認のみ行いたい備品に対して、RFIDタグを使用した棚卸が可能です。
RFIDを使用した棚卸は、一括で備品の所在を確認できるため、非常に便利です。
RFIDを使用した棚卸の流れ
1. リーダーとスマートフォンを繋げる
RFIDのリーダーのバッテリーが充電されていることを確認し、電源をオンにしてスマートフォンをセットします。
2. アイテムとRFIDを紐付ける
備品管理クラウドのスマホアプリを開き、すでに登録されているアイテムまたは、新規登録するアイテムとRFIDを紐付けます。
3. 棚卸計画を作成する
棚卸管理者が、どの場所でどのアイテムの棚卸を、誰がいつまでに実施するのかなどを設定して棚卸計画を作成します。
棚卸計画を作成すると、棚卸責任者と実施担当者のもとへ、棚卸の依頼メールが送信されます。
棚卸依頼が届いたら、リンクから棚卸を行う備品の一覧画面に遷移します。
4. 棚卸の実施
棚卸依頼メールからリンクをクリックすると、棚卸の一覧表に遷移します。
ページ上部のRFIDを使った棚卸しをクリックし、棚卸をしたい備品がある場所に向かってRFIDリーダーのトリガーを引きます。
読み取りが完了すると、「報告済み」のチェックがつくようになります。
5. 棚卸を完了する
実施者が棚卸を実施していくと、棚卸の計画ページに報告内容が棚卸一覧ページに戻ると同時に自動で反映されていきます。
棚卸管理者はダッシュボードで、報告済み、故障品、紛失、未実施のアイテムがいくつあるのか、すぐに確認できます。
すべての棚卸が実施されたら棚卸を終了させます。
このように、『備品管理クラウド』は、RFIDを活用した棚卸機能で備品管理を効率化します。
『備品管理クラウド』に少しでも興味を持たれた場合は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
まとめ
RFIDとICタグを活用することで、備品管理の効率化、コスト削減、ヒューマンエラーの防止が実現できます。特に、総務部門の方々にとって、業務の負担軽減につながる有力な手段となるでしょう。今後、さらに多くの企業でRFID技術の導入が進むことが予想されるため、ぜひ活用を検討してみてください。
以上のように、ICタグやRFIDを理解し、適切に活用することで、業務の効率化が期待できます。今後の技術革新にも注目しながら、最適なシステムを導入してみてはいかがでしょうか。
RFIDを活用した備品管理なら備品管理クラウド
『備品管理クラウド』は、RFIDを利用した棚卸機能を提供しており、一括で備品の所在を確認することで棚卸作業を効率化することができます。
少しでも気になる方は下記よりお気軽にお問い合わせください。

 一覧に戻る
一覧に戻る
 お問い合わせ
お問い合わせ